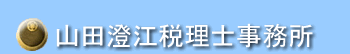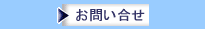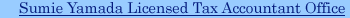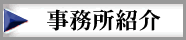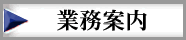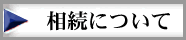平成15年度の税制改正により、消費税の事業者免税点が3,000万円から1,000万円へ、簡易課税制度の適用上限が2億円から5,000万円に引き下げられました。
これにより、新たに課税事業者となる事業者が大幅に増えることになりました。個人事業者では、来年の確定申告で始めて消費税の申告を経験する方も多いと思います。
そこで、消費税の用語について、いくつか説明します。
< 基準期間 >
消費税の納税義務が免除されるかどうか、簡易課税制度を適用できるかどうかを判断する基準となる期間をいい、個人事業者については、その年の前々年、法人については、前々事業年度(事業年度
が1年の場合)をいいます。
ですから、個人事業者の場合、平成15年における課税売上高が1,000万円を超えると平成17年が課税事業者となります。
< 課税事業者 >
事業者のうち基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者、及び「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている事業者をいいます。
< 課税期間 >
納付すべき消費税の計算の基礎となる期間で、原則として、個人事業者は暦年、法人は事業年度をいいます。
< 簡易課税制度 >
その課税期間における課税標準額に対する消費税額を基にして、仕入控除税額を計算する制度をいいます。
具体的には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率(第一種事 業90%、第二種事業80パーセント、第三種事業70パーセント、
第四種事業60パーセント、第五種事業50パーセント)を掛けて計算した金額が仕入控除税額とみなされる制度です。
したがって、実際の課税仕入れ等に係る消費税額を計算する必要はなく、課税売上高のみから納付する消費税額を算出することができます。